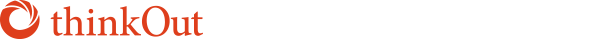日本最高学府の大学である東京大学で、最上位の役職である「総長」を担う人物はどのように考え抜いてきたのか——。今回話を聞いたのは第28代東大総長で、現在は三菱総合研究所の理事長をしている小宮山宏(こみやま・ひろし) 氏です 。
小宮山氏は過去に講師や教授を経験し、学生とのコミュニケーションを多くとってきました。失敗も経験した上で現在のスタイルに至ったと言います。考え抜く方法と共に、部下のマネジメントに苦しんでいるビジネスパーソンへ、大きなヒントとなる話を聞いてきました。その後編記事です。

この記事のポイント
- 自分で考える前にググらない
- 若者の力を最大限に発揮するため、一緒に考える環境をつくろう
ググらないことが大切 研究前に他の論文は読まない
“考え抜く”ために必要なことはありますか?
すぐググらないことですよ。Googleは便利ですが「すぐに答えに行き着く」というのは、デメリットもあると知ることが必要です。
特に何かを始める時。まず最初に他人のやり方を知ってしまうと、自分のやり方ができなくなってしまいます。人間はそんなに強くないので、最初に知った他人の枠組の中で考えてしまいますからね。
それは大きなデメリットです。
わたしは学生にはいつも、「研究前に、まず論文を読む」のは止めよう、と伝えています。
頭のいい学生ほど、これをやってしまうんです。もし自分の研究に近いテーマがあったら「もう研究されているからやめよう」ということになりがちです。
大切なのはそこではない。同じ研究でも、社会は刻一刻と変わっているのだから課題が違う。同じ研究でもその人が課題に思っていることへアプローチする研究であれば、別の結果が出ることだってある。
だから先に他の人が書いた論文なんて読まなくていい。読まないほうがいい。まずは自分で考えて研究計画を自分で立てることが重要なんです。読むのはその後。

社会を良くしたいという好奇心
小宮山さんが現在、興味があることは何ですか?
社会を良くするということです。現在だけじゃなく、ずっとそうですね。社会を良くすることって、課題が大きいじゃないですか。1つの課題が解決しても、新しい課題が常に出てくる。
振り返ると、わたしは「Student Power」の世代、日本でも東大闘争という社会情勢の中で学生時代を過ごしたんですが、それが大きいかもしれないですね。
当時「ゲバ棒を振って日本が良くなる」とは思わなかった。とはいえ、じゃあ何をすればいいのかはわからなかった。研究はおもしろかったから始めただけだけど、どうしたら研究を通じて社会をもっと良くできるだろうか、とは常に考えてきました。
社会を変えるのは若者の力がカギになる
これから社会を変えていく上で何が大切だと思いますか?
私の経験上「若者は素晴らしい」ということです。若者は大人を変える力がある。
組織や地域に派閥があり、何をやってもうまくいかなかったことを、学生を中心とした若者が動くことで大人たちの意識が変わっていく事例をこれまでたくさん見てきました。
あとはシニア、大学生、子どもというような、世代の違う人たちが交流したり、意見を言い合ったりする場所がとても大切だと思います。昔は家庭や地域でそれが実現できていましたが、今は難しい。だからそういう場所を意図的にたくさん作っていきたいですね。
そのような場で、何かやるときには「一緒にやる」ということが大切です。若者に「やらせる」「まかせる」はタイミングを間違えば責任放棄になってしまいます。上の世代はそうなっていないか注意しないといけない。
あくまで立場は対等です。意見を言ってもらえる関係をつくる。そのためには、やっぱりシニアは威張ったらダメなんですよ。

[ライター:桜口アサミ]
プロフィール
インタビュイー
小宮山 宏(こみやま・ひろし)氏

三菱総合研究所(MRI)理事長。工学博士。専門は化学システム工学、地球環境工学、機能性材料工学、CVD反応工学。1944年、栃木県生まれ。1972年に東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学工学部講師や教授、副学長などを経て2005年4月、第28代東大総長に就任。2009年3月で任期満了により総長を退き、現職。