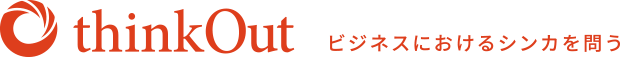隆盛を極めた企業が倒産に至る理由
コダックやリーマン・ブラザーズ、鈴木商店など、古今東西、倒産してしまった会社25社の背景とそこからの学びをまとめた『世界「倒産」図鑑』という書籍を昨年末に執筆しました。
ここまで隆盛を極めた企業がなぜ倒産に至ったのか。経営の仕組みそのものの問題もあれば、人間関係の問題もありました。自ら時限爆弾を仕込んで、時間差で爆発したような自業自得とも思えるケースもあれば、時代の不可抗力のようなものに巻き込まれつつもギリギリまで努力の上、力及ばず倒れていったようなケースもありました(涙なしでは語れないようなストーリーも数知れず)。
当たり前ですが、置かれた時代背景や業種によって、その倒産の理由はケースバイケース。一概に共通項を括れるものではありません。
しかし、倒産してしまった企業の内側に蔓延る「考え方」に着目し、敢えてその共通項を仮説ベースで導くのであれば、それは「哲学的な問いの不足」ということにあるのではないかと考えています。
「哲学的な問い」と「実務的な問い」とは
では「哲学的な問い」とは何か?それは、根源的かつ抽象的な問いと言い換えることができます。
たとえば、アパレル業を営むのであれば、「人はなぜ洋服を着るのか?人はなぜ洋服を買うのか?」という問いに向き合うことです。出版業界であれば、「人はなぜ本を読むのか?」「人はなぜ学ぶのか?」という問いに向き合うべきでしょう。
これらの問いは根源的、抽象的がゆえに、明確な答えが出せるわけではありません。おそらく答えは人によって異なるでしょう。したがって時間をかけた議論や対話が必要になります。
この「哲学的な問い」の対極にあるのが、表層的であり具体的でもある「実務的な問い」です。
たとえば、「売上5%増をどう達成するか?」であったり、「新規顧客数を昨年対比2割増やすにはどうするか?」という問いが該当します。
これらの問いは、おそらく多くの人が日常的に考えている問いであり、企業によってはKPIとしてしっかり管理されている組織もあるでしょう。
そして、私たちの脳内は、無意識でいれば「実務的な問い」で満たされていきます。実務的な問いは、哲学的な問いと比較して、答えのブレが少なく、正解が見つかりやすい類のものです。だからこそ、解法を早く見出した人や組織は短期的に急成長していきます。
変化に必要な「哲学的な問い」
しかし、気を付けなくてはならないのは、そういった「実務的な問い」に向き合い続けることは、短期的な達成感を生み出してくれますが、長期的には変化に弱い組織を作ってしまう、ということです。「実務的な問い」は、すぐに賞味期限切れを起こしてしまいます。
購買行動の在り方そのものが変革を迎えている世の中で、「リアル店舗の顧客満足度向上」だけに向き合っていても意味がないでしょう。本当は環境に合わせて問いの方向性を変えなくてはならないのに、「実務的な問い」の引力に負けて、わかりやすく答えの出しやすい問いに向き合い続けてしまう。
そんな組織は、変化のタイミングで、再度本質的な問いに向き合うマインドセットの切り替えができず、大きな変革に踏み出せなくなります。
「自社しか知らず、偶像崇拝で井の中の蛙になっている皆さん・・・指示しなければ何もしないと、外部の人々からそごうの社員への評価は低いのです」
これは、倒産(民事再生法申請)後、経営再建のためにそごうに乗り込んだ和田繁明・元西武百貨店会長からの、社内報でそごう社員に向けられたメッセージです。
想像するに、おそらく当時のそごうの現場では、限定的な「実務的な問い」にしか向き合ってこなかったのかもしれません。だから、百貨店のビジネスモデルそのものが変わりつつあっても、問いの抽象度を高めることができなかった。このように、自ら問いの方向性を変えて考えることのできない個々人の状態が、外部の和田さんには「指示しなければ何もしない社員」と見えたのかもしれません。
もちろん「実務的な問い」に向き合うことも重要です。日々のキャッシュは、この「実務的な問い」への答えになります。言うまでもなく、その問いに答えなければ業績を上げることはできません。
しかし、同時に、それだけではダメだということです。
組織内で、より根源的な「哲学的な問い」に向き合う時間を少しでも担保できるか。これが、変化への対応の強さを決めるのです。
問いの方向性をコントロールするための思考力を鍛えよう
昨今、ビジネス書においても、アート関係の本や哲学関係の本が密かなブームになっています。特に「アート」というタイトルがつく本は、書店でもよく見かけるようになり、ヒット本も増えてきているように思います。
この背景には、ビジネスパーソンの間で具体的で表層的な「実務的な問い」に向き合い続けることへの潜在的な懸念があるのだと私は見ています。
つまり、アートのように不明確でよくわからないこと、正解のないこと、短期的には答えの出せないことに向き合う胆力の重要性や価値に、多くの人が気づき始めているのではないかと。もしそうだとすれば、そのムーブメントは歓迎すべきだと思います。
今、私たちの目の前にある仕事は、何かを実現するための「手段」でしかありません。その手段はどんな「目的」を実現するためのものなのか。私たちは果たして何を実現するために働いているのか?
抽象的で答えの出しにくいこういった「哲学的な問い」に正しく向き合い、その問いを抱え続け、時間をかけて答えを出していくことは、組織を永続的に発展させていくために必要なことです。具体的でわかりやすい「実務的な問い」の奴隷にはなってはなりません。
このような問いの方向性をコントロールしていくための思考力が、いま、私たちに求められているのではないでしょうか。
プロフィール
本コラムの著者
荒木 博行(あらき・ひろゆき)氏

株式会社学びデザイン 代表取締役社長
株式会社フライヤー 取締役COO
著書に『見るだけでわかる! ビジネス書図鑑』『見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 これからの教養編』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『世界「倒産」図鑑』(日経BP)など。
-
次の記事を読むAIの提案力に勝る法人営業マンの強み

関連記事
ロジカル思考の限界(前編)