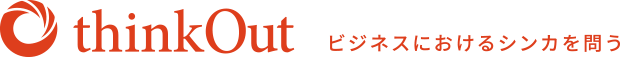2.-1「筋の良い仮説」はどう生まれるのか
どうすれば「筋の良い仮説」を思いつくことができるのか。実は、これには確立された方法論がないのが実情です。
では、仮説を出す際に頭の中で何をしているのかと問われれば、左脳的(論理的)に「考える」よりも、右脳的(感覚的)に「感じる」という表現がしっくりきます。
すなわちそこに巧拙があるとすれば、「感じる」のがうまい人とそうではない人がいる、ということになりますが、これは多くのコンサルタントの成長過程を見てきた中でも体感することです。では、人はどうやって仮説を導き出すのか。
何らかの入力(インプット)があり、それが脳内で情報加工(プロセス)され、仮説という出力(アウトプット)が出てくる、というステップで、どのようなことが起こっているのかを分解して考えていきたいと思います。
仮説を出すためにコンサルタントがやることはまずは徹底的な情報のインプットです。
「仮説なきリサーチは効率が悪い」のは一面の真実ですが、一方で仮説を考えるためにも一定のインプットは必要です。
新しい業界やテーマのプロジェクトが始まったら最初に「本は(本屋の)“棚”で買う」「業界誌2年分×3種類」などといわれ、まずは徹底的に情報を詰め込むことを基本動作として指導されました。
この際に重要なのは、短期間で、全体像から細部まで様々なレイヤーでの情報に直接触れること、特に現場の加工されていない生の情報に触れることが極めて重要になります。
生の情報とは、ビジネスでいえばサービスを提供している現場(自分が消費者として体験することも含む)、お客さんの生の声、現場でサービスを提供している従業員の声などなどです。
そのような情報を入力(インプット)すると、それが脳内で情報加工(プロセス)され、そこから新しい仮説(アウトプット)が出てくるということなのですが、では情報をインプットすれば誰もが「筋の良い仮説」を出せるのかというとそうではなく、明確に個人差が出ます。
これには大きく2つの要因があるように思います。一つは情報加工のプロセスの違い、もう一つはインプットそのものの違いです。
2.-2 情報を認識する「枠組み」を持つ

一つ目の情報加工のプロセスですが、その巧拙を分けるのは一言でいえば「自分なりの情報を整理する枠組みを持っているか」です。
人間はこれまでの経験や知識を自分の中で整理して記憶しています。
整理するにはそれぞれの情報に「ラベル」が必要となり、その「ラベル」を貼るというのはすなわち物事を「抽象化」して捉える作業ということになります。例えば、ある事業において起こった事象を単なる一つの事例としてとらえるだけではなく、
- 〇〇型の事業ではこういうことが起こる
- こういう条件がある場合にこういうことが起こる
のように、一旦抽象化して次元を上げて捉えられると、次に「〇〇型の事業」や「こういう条件」に遭遇した際にカンが働くことになります。
日々の情報収集も同様で、よく色々な情報に触れるのが良いといわれますが、そこでどれだけ情報を「咀嚼」できているかで、触れた情報を後にどれだけ再活用できるかが決まっていきます。
できている人とできていない人の差も、これによって加速度的に開いていくことになります。
新しいアイディアとは、既にあるものの新しい組み合わせ=「新結合」に過ぎない、という言葉がありますが、突拍子もない天から降ってきたような仮説を思いつく人も、実は過去の知識や経験と目の前の事象を無意識のうちに結び付けていることがほとんどです。
この情報の「咀嚼力」を持った上で、経験や情報を蓄積していくことが「筋の良い仮説」を生み出すための一つの条件になります。
経験豊富なコンサルタントが少しの情報から「おそらくこうだろう」という精度の高い仮説を立てられるのには、こういう背景があります。
2.-3 思考を捨て、あるがままを「感じる」
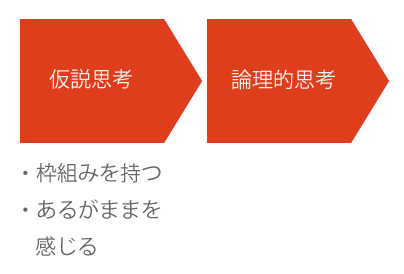
仮説の精度を左右する、より重要な二つ目の要因が、インプットそのものの質です。
仮説を考える初期の段階でなるべく多くの情報に触れる必要性は既に述べましたが、同じ情報に触れてもそこからどのような情報を知覚できるか、感じ取ることができるかということには個人差があり、そこでも巧拙が分かれることになります。
この問題を考えるうえでは、そもそも人間は物事をどのように認識しているのか、ということに立ち返る必要があります。
「人間は物事をどう認識するのか?」と問うたら「目で見て、耳で聞いて、など五感を使ってに決まってるではないか」という答えが返ってくると思いますが、本当にそうでしょうか。
例えば最近はAIの世界で画像認識技術の研究が進んでいますが、視覚をつかさどる目は単独ではカメラと同じであり、光学的な情報(明るさや色)をデータとして脳に伝えているだけの器官です。
顕微鏡で大きく拡大すれば色がついたドットの連続でしかない画像情報から、それが「猫である」と「認識」するには、その特徴量をパターン認識し、結果として輪郭を捉えて初めて「猫である」と認識できるようになる、という学習の過程をたどります。
逆に言えばその情報がないまま画像を見ても「猫である」と認識できず、単なる色の連続にしか見えません。
この例はかなり単純化していますが、結局人間は「自分が事前に認識しているものしか見えない」もっと言えば「見たいものしか見ない」生き物なのです。
情報の海に飛び込む際にやってはいけないことの一つは、先入観を持って見るということです。そうすると「見たい事実」しか見えなくなります。
こういった先入観は自分の置かれた環境、トラウマ的なモノも含めた過去の経験、それまで(場合によっては幼少期から)育んできた価値観、社会的に求められる自分の役割などによって、知らず知らずのうちに形成されており、人は皆そういった一種の「レンズ」を通して世の中を見ている、ということになります。
もちろん、それによって認知が効率化されるという側面もありますが、一方で目の前にあるものをあるがまま認識する際には、先入観は大きな障害になります。
目の前のものをあるがままに認識するには、先入観=「思考によって形成されたレンズ」を一度外したうえで、まずは価値判断を保留し、あるがままを「感じる」ことが何より重要になるのです。
その意味でも、加工された2次情報ではなく、生の1次情報に触れることは重要です。
例えばあるサービスのユーザーに感想を聞いたとしても、「満足しています」という言葉を発したという事実だけでなく、それを話した時の表情やテンションからニュアンスを「感じる」ことも重要ですし、ちょっとした違和感が重要な気づきになることもままあります。
「第三者であること」がコンサルタントの価値たりえるのも、長年の経験から一種のレンズを通して事業を見てしまうクライアントとは違って、コンサルタントは「あるがままの事業の状態」に「違和感」を覚えることができ、そこから課題を発見することができる、というメカニズムになっているのが大きな要因の一つです。
「そもそもどうしてこうなってるんですか?」「なぜこれでなければいけないんですか」などの素朴な疑問をいかに持てるか、というのはコンサルタントの重要な素養であり、役割の一つになります。
プロフィール
本コラムの著者
占部 伸一郎(うらべ・しんいちろう)氏

2001年東京大学経済学部卒。新卒で株式会社コーポレイトディレクションに入社し、19年間の間、一貫してコンサルタントとして活動。2012年にパートナー就任し、CDIの経営に携わる。途中、三菱商事の金融事業本部M&Aユニットへの出向経験がある。Fringe81株式会社社外取締役を兼任。経済ニュースメディア「Newspicks」プロピッカー