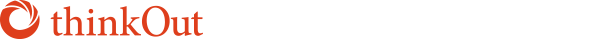3.「考える」の終着点は「主観的な意見を述べる」こと

順番が前後しましたが、実際の思考の順序を図のように整理しました。ここまで「感じる」「仮説を生み出す」「論理的に考える」というプロセスを見てきました。
では、論理的に考えて結果が出ればそれは真に考えたことになるのでしょうか。もちろんそれで十分なこともありますが多くの場合にはもう一歩思考を深めることを求められます。
シンクタンクとコンサルティング会社の違いを説明する際、よく「Sky is blue(空は青い)」と状況を正しく調査するのがシンクタンク、「So what?(では、どうするか。傘を持っていくべきなのか)」の問いに答えるのがコンサルタント、と表現されます。
例えばコップに半分水が入っているのが事実(Fact)として、「半分しかない」(=有望でない)と見るのか、「半分も残っている」(=チャンスだ)と見るのかは多分に主観による判断が必要ですし、それを判断した上で、ではどうすべきなのか、ということにも多分に価値判断が求められます。
コンサルタントは「客観的な第三者が“正解を提案する”職業である」といういわれ方をすることも多く、もちろんそういう側面もあります。
しかし、残念ながら経営の意思決定に「絶対」が無い中では、「提案」も言ってしまえば「仮説」でしかありません。結局のところ、限られた情報と不確実性の中での意思決定をしなくてはならない局面で求められることは、「同じ情報を頭に入れ、論理的に考えることは考え尽くしたうえで、結局コンサルタント個人としてどう考えるのか?」つまりは「主観的な個人の意見」であることが多いと実感します。
経営の意思決定は常に不確実性の中で行われます。MBAなどで行われるケーススタディも、今ある限られた情報の中で意思決定することの訓練とも言えます。
さらに、そのような意思決定をする際には「論理的な正しさ」、ビジネスで言えば儲かるかどうかということだけでなく、真美善でいう「美」や「善」の要素も重要になります。
その企業なりの、その人なりの価値観や倫理観にも照らし合わせた上で、生身の人間としてどう判断するか、そこにはFact(事実)&Logic(論理)だけでない人間臭いプロセスが重要になるのです。
4.究極の問いは「何を考えるべきか考える」こと
以上、ある論点があった際に、「感じる」ことから始まって仮説を立て、論理的に検証し、それに対しての示唆とりわけ主観的な見解にまで昇華する、というプロセスを通して、ビジネスにおける「考える」について考察してきました。
実際には、ビジネス上の問題解決の基本的な流れであるこの一連のプロセスをひっくるめて「考える」と言っていたりすることが多いです。
「ある論点があった際に」といいました。では、その「論点」はどこから出てくるのでしょうか。
実は、一番難しい究極の問いは、この「何を考えるべきか考える」ということです。
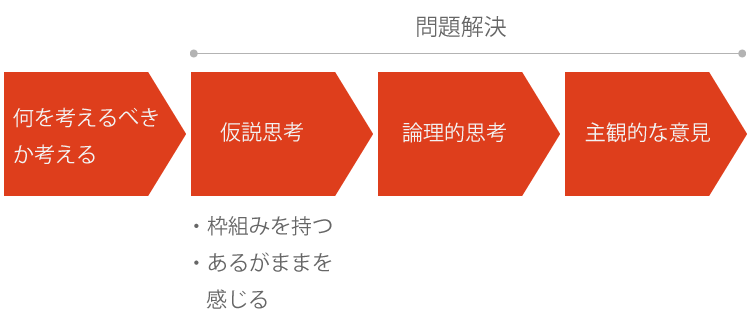
元マッキンゼーの安宅和人さんが書いた『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』という名著がありますが、まさに題名の通りで、どのようなイシュー(論点)を設定すべきかということ自体が極めて重要であり、「考える」ことの核心といえます。
コンサルティングの仕事においても、クライアントから最初に相談される問題意識が、実は本当に解くべき問題でないこともままあります。依頼人の時にはあいまいな課題意識を伺い、その背景を深く掘り下げていくのはもちろん、一方でその会社が置かれた環境や積み重ねてきた歴史、大切にしてきた理念など、様々な情報を勘案した上で“今、その会社にとって取り組むべき課題は何か”を定めることが重要な第一歩になります。
具体的には、プロジェクトの設計をまとめた提案書を作成する際に
- どのような問いに答えるプロジェクトを行うべきか
- その問いに答える際に解くべき問い(論点)は何か
を明確にすることが求められます。
もちろんプロジェクトが進む中でその論点は柔軟に見直されていきますが、最初の時点で「確かにその論点に答えていけば問題に答えられそうだな」とお互いに共通認識を作ることが出発点になります。
AIの進化によって、「問題をいかに解くか」という領域では、徐々に人間は必要とされなくなっていくのかもしれません。そんな中で、ビジネスにおいて人間が「考える」ということの意味を突き詰めると、この「何を考えるべきか考える」ということに集約されていくようにも思えます。

プロフィール
本コラムの著者
占部 伸一郎(うらべ・しんいちろう)氏

2001年東京大学経済学部卒。新卒で株式会社コーポレイトディレクションに入社し、19年間の間、一貫してコンサルタントとして活動。2012年にパートナー就任し、CDIの経営に携わる。途中、三菱商事の金融事業本部M&Aユニットへの出向経験がある。Fringe81株式会社社外取締役を兼任。経済ニュースメディア「Newspicks」プロピッカー

関連記事
困難を味方にする力―経済学の知恵―