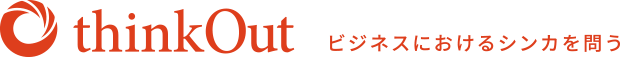前回は、私のコンサルティング経験を踏まえ、ビジネス現場の臨床的視点から以下の点を述べた。
- 考えることに関して、真に成長し他者と差別化するために必要なのは、手法論を身につけるより、思考習慣を築くことである
- 与えられたテーマの問題解決より、その周辺の何もないところで「気づく」ことの価値が増している
- 「気づく」ためには、能動的に自分に「問いかける」ことが有効であり、これを思考習慣化すべきである
- 私の経験から、特に重要な問いかけの観点は次の4つ:(1)分ける(2)疑う(3)他人の立場で(4)で、どうするのか。これらの習慣化を優先すべきである
前回は(1)について解説したので、今回は(2)以降の議論を進める。これらはコンサルタントだけでなく、ビジネスパーソンの新人~マネージャー中堅層を対象とした、考える力を高めるための議論である。
[第1回の記事はこちら / 第2回の記事はこちら]
気づきをもたらす問いかけの観点 (2) 疑う
自分に問いかけるべき2つ目の観点は、人の話をそのまま受け入れず「本当か?」といったん疑ってみることだ。
ある大企業の社長から「当社は新規事業が失敗してもなかなか撤退できないので、撤退基準を明確にしたい」という話があった。
私は外部コンサルタントとして、「基準を作ることには反対しないが、基準などなくても撤退を決められる会社も多い。むしろそういう議論・決断をしてこなかった役員会に問題はないか?」と提起した。
「撤退基準がないから撤退できない」はもっともらしく聞こえ、その会社の文化の中では正しいロジックなのだろう。しかし「本当か?」と疑うと、別の見方も出てくる。
この話から「ある大企業の・・・話があった」の2行を切り出して「どう思うか?」と問われれば、私のような疑問を提示できる人は少なくないだろう。クリティカルシンキングの研修で出てくるような話だ。ところが実際のビジネスでは、まず「この2行をどう思うか?」の部分を誰も聞いてくれない。
まして実際には、社長の話は100行に及ぶようなボリュームだった。その場にいた社長以外の人の発言も含めれば、つまり会議全体の情報量としては、300行分ぐらいあっただろう。ここで重要なのは、その300行分の文章から先ほどの2行がおかしいと気づけるかどうかである。それが、考えることのできる人とできない人の差分である。
「ある大企業の・・・話があった」の2行を切り出して「どう思うか?」と質問され、それに対する答えを出すには手法論を身につければ済む話だろう。しかし、誰に聞かれることもなく、300行の中から2行の違和感に気づくのは思考習慣の有無で決まる。これらは別のコンピテンシーである。
企業内では、もっともらしく聞こえるがために汎用されるフレーズがある。「役割を明確にすべき」「権限委譲を進めよう」「情報を共有すべき」「コミュニケーションを取ろう」「基準を明確にすべき」「成長市場を狙おう」等だ。
これらはもちろん妥当・的確な場合も多いが、概念として耳触りがいいので、思考停止に繋がりやすいという落とし穴がある。
ひとつひとつ、いったんは疑うことを習慣づけることが必要だ。
もちろんこれらのフレーズに限らず、ビジネスで聞かれるちょっとしたコメント、特に伝聞情報などは、まずきちんと事実を確認することから始める必要がある。同時に、意図や真意は別にあるのではないかと考えて再確認・再定義することが重要であり、そのためにも「疑う」プロセスが必要だ。
社会問題などの評論家は、敢えて世間の多数派意見に同意せず反対のことを言う「逆バリ」が多いが、ビジネスにおいてもいわば「逆バリ」のスタンスでとりあえず疑ってみることは、有効な場合が多く、習慣化すべきことである。
気づきをもたらす問いかけの観点 (3)他人の立場で
以下は、実例をもとに作成したコンサルタント向けの研修用ケースの概要だ。あなたはどう考えるだろうか。
- ある企業のトップから「最近、全社組織改革を行った。社内に強い反対はあったが長期的には必要な改革であると考え、断行した。その後の状況を社員にヒアリングし、コンサルタントとしてどう見えるかを教えて欲しい」と依頼があった。
- 社員20名に話を聞くと、8割以上の人が組織改革のもたらしたネガティブな側面を語り、改善すべき問題として10数項目以上を挙げた
- 残りの2割弱の人は「問題はなかった。問題に見えるものは改善可能である」と指摘した
- こういった状況で、あなたはコンサルタントとして顧客トップに何を報告するか
実際の研修では「こういう問題があった」「それらは問題ではない」という具体的なヒアリング結果を3ページ分を補助資料として提供し、問いへの答えを受講者に考えてもらった。
やってもらうと受講者のほとんどが問題項目を整理・体系化し、論点化して、これが当該企業の課題であるといった考察を上手に書く。イシューツリーなどの手法論を駆使する人も多い。
ところがこれは引っ掛け問題であり、このような考察だけでは不十分である。
組織改革は当然何らかの狙い(メリット)があって行われたはずであるにもかかわらず、社員の声はデメリットに集中し、メリットに言及した社員はいなかった。
誰一人としてメリットに興味も問題意識もなく、声が挙がらなかったこと自体が大きな問題なのであり、声に出た部分だけをいくら整理しても不十分というオチの、意地悪な出題だったわけだ。
これは私が実際に仕事で経験した例だが、最初は私もヒアリングで聞かれた声をまとめる作業をした。
ところがその結果を顧客トップの立場で見ると「反発があるのは当初からわかっていて、敢えてやったことだ。それを問題だと報告されても」と反応することが想定された(トップ自ら「強い反対があったが」と最初に述べている)。また、トップの興味関心は当然、改革をしようとしたそもそもの狙いが実現できそうかどうかであるはずだ。
それで考え直し「もともとやりたいこと=改革に期待するメリットが社員の頭にすら入ってない」事実に着眼し「せっかく行った改革であるが、その狙いは実現できないだろう」との考察をして報告すると、顧客はそれに驚きつつも、調査自体には満足して頂いた。
このケースは今まで300人以上の若手コンサルタントにやってもらったが、コメントの分析・整理に終始せず、私と同様の観点で考えられたのは3人くらいだった。
これは、大量の情報に思考が振られ、作業に没入してしまい、他人(顧客トップ)の立場で考えるという観点を見落としてしまうからだ。もし「あなたのまとめたヒアリング結果を顧客の立場で見ると、どう思う?顧客になりきって考えてみて」とガイドすれば、本当の問題点に気づく若手も少なくないだろう。
また、以前、知り合いのベンチャー企業の社長にこのケースを見せた際は、問題の整理をするまでもなく「社長のやりたいことが伝わってないということだね。私ならそれを指摘する」と即座に見抜いた。現場上がりでいわゆるビジネス教育的なものとは無縁の方だが、社長の立場で考える習慣が確立しているからだ。
ここではコンサルタント向けの話を例として示したが、同様の事象は一般ビジネスの各領域にてあり得ることだと思う。また、相手が経営トップである場合に限らず、上司でも取引先でも一般消費者でもあり得ることだ。
もちろん他人の思考・心理・気持ちを理解するのは容易なことではなく「考えたが読み切れなかった」をゼロにすることはできない。だが「考えることをつい見落とした」は避けるべきだ。
「他人の立場で」とは手垢のついたフレーズだが、何もないところで、誰にも言われなくてもそれに気づけるかどうかが重要であり、自分に問いかけることを思考習慣として築くべきなのだ。
気づきをもたらす問いかけの観点 (4)で、どうするのか
会議を行うと、現状分析(問題特定や原因究明、そのためのデータ分析)に時間が割かれ、残り時間が少なくなったところでふと我に返ったように「今後どうするのか」の議論が行われることがある。
私もコンサルタントなので分析は重視するが、それでも最近は企業内では、どちらかといえば対策よりも分析に議論の比重が偏ることが多いように思う。どうするかより、何が悪いかの議論だ。
参加者がもっと早く「で、どうするのか」を問いかけていたら、議論はより効率的に進むだろう。
また、対策につながらない議論も多い。若い社員と「当社を成長させるためにはどうすればよいか」をテーマに議論すると、「成長とは売上ですか、利益ですか、社員数ですか?」「まずは成長の定義をはっきりさせないと」等、前提条件や問題定義に関心が向かう傾向が見られる。
そういった疑問は大事だが、なるべく早く「で、どうするのか」の議論を進める方がよい。仮に答えがA案・B案・C案と出て、売上成長ならA案、利益成長ならB案となったのであれば、その時点で初めて「ここでの成長は売上か利益か」を議論すればよい。
現実には、売上でも利益でも社員数でもA〜C案の良し悪しは変わらず、最初の議論はあってもなくても結論は変わらないということも多い。
りんごが落ちる現象を見てなぜ落ちたかの原因を探ると、「風が吹いたから」「枝が弱いから」「下にネットがないから」と多様な次元の考察が可能である。
これらは実は「風から守る」「枝を補強する」「ネットを張る」といった対策が頭に描かれており、対策から逆算したときに不足していることが原因として定義されている。つまり原因と対策をほぼ同時に考えているのであり、議論の方向性は正しい。
もちろん対策だけが先走り過ぎてもいけないが、時間をかけて真理を追求した結果「引力があるから落ちた」という結論に達したとしても、対策がない以上、ビジネスとしては有効な原因分析とはいえない。
思考はどうしても現状や問題(何が悪いのか)に向かいがちだ。その頭を振り払うために「で、どうするのか」を常に問いかける思考習慣をつけることが有効だ。
思考力を磨く、4つの問いかけの習慣化
以上、4つの問いかけの観点を解説した。おそらく、難解でも斬新でもないという印象をもったことだろう。自分は大体やっている、できているという人もいるかもしれない。それはきっと正しい。なぜならここに挙げた「気づいた後」の工程は、多くの人が実際に難なくできることだからだ。
しかし私が指摘したいのは、ビジネスにおいて気づかずに通り過ぎてしまう部分がいかに多いかということ、そして、そこに気づくか気づかないかが「考える技術」を左右するということだ。
世の中のビジネス研修や著書も「気づいた後」の話を扱っているものが多く、もはや、誰もが気づけるような問題点や気づいた後の対応で差別化を図ることは難しい。
「考える技術」を高めるためには、自分で能動的に問いかけることの習慣化が必要なのである。
どのように問いかけるか。これには2種類ある。
一つはその場で問いかけることだ。例えば、会議や顧客と交渉するとき、報告書を作成するとき、メールを書くとき、あるいは何かを難しい問題だと感じたときに、紹介した4つの観点で自分に問いかければよい。
もう一つは、その場から離れて、例えば1日の終わりに振り返って、自分なりに考え直す方法である。今日聞いたあの人の話を分けてみよう、あれは本当なのか?彼の立場ならどう考えるか、あの懸案は結局どうするのか?と、問いかけるのだ。
それをやり続ければ、必ずよい成果につながるだろう。
最初は100のうち1つ気づきにつながればいいくらいに思う方がいいかもしれない。それでも諦めずに丹念に続けるのだ。まずは意識的に続けていくことで、無意識に問いかけることができる思考習慣を築いていくことを目指す。
次回は、この思考習慣を確立して「考えられる人」に成長するための方法を議論していく。
プロフィール
本コラムの著者
細田 和典(ほそだ かずのり)氏

東京大学工学部、同大学院卒業後、株式会社コーポレイト ディレクション、ブーズ・アンド・カンパニー(現PwCコンサルティング合同会社)にて25年以上にわたり経営コンサルティングを経験。 その後、原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与、プライスウォーターハウスクーパース株式会社顧問を務めた。 株式会社プロレド・パートナーズ監査役。

関連記事
困難を味方にする力―経済学の知恵―-
前の記事を読む考える技術【第2回】基盤とすべき思考習慣(1)
-
次の記事を読む考える技術【第4回】思考習慣の確立に向けて